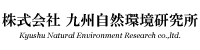会社の歴史
| 1994年 | 「エコ・リサーチ」という名称で創業 1994年より3年間、熊本県で初めてとなるシカの生息密度調査を実施 |
|---|---|
| 1995年 | 菊陽町に事務所をおき環境調査を本格的に始める 3名で有限会社九州自然環境研究所として法人化 O川ダムにおいて、クマタカ調査を先駆的に取組む |
| 1998年 | S高速道路において、動物の環境選択性から、良質環境区域の推定を実施 |
| 1999年 | 株式会社へ組織変更 |
| 2000年 | 県立博物館をフィールドミュージアムとして提案し、生物生態資源の発掘調査を4年間実施 |
| 2003年 | 農林水産研究高度化事業プロジェクトの一員に選ばれ、安全堅牢でイノシシが入り易い捕獲器の開発を始める |
| 2004年 | ISO14001:2004認証を収得 |
| 2005年 | イノシシ捕獲器 「シシトレール」完成、熊本県の経営革新支援事業の認定 創業10周年記念式典開催 |
| 2006年 | 熊本県戦略的事業化推進事業費補助金を受け、「シシトレール」の販売を始める |
| 2007年 | 鳥獣害の補助金制度の活用法をコンサルティング |
| 2008年 | 農村整備事業で環境調査導入。圃場整備等に伴う環境調査を実施 |
| 2009年 | 林野庁九州森林管理局発注の「野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備調査事業」を受注し、シカの生態調査及び捕獲手法の検討を始める |
| 2011年 | シカの被害から希少な植物種を守るための植生保護柵を九州中央山地を中心に設置。 宇土半島のクリハラリスの調査を実施 |
| 2012年 | 熊本県内のアライグマの生息確認調査を市町村の委託で実施 2012年から、保護林モニタリング調査等業務を実施 |
| 2013年 | 輪番移動式捕獲法というシカの効率的、効果的な捕獲手法の確立 |
| 2014年 | 公共事業として、有害鳥獣対策を実施 創業20周年記念式典開催 中園敏之から中園朝子へ所長を交代 環境省の九州地方アライグマ防除啓発事業を実施 2014年から九州森林管理局の森林保全再生整備に係る鳥獣の誘引捕獲事業を受注する |
| 2015年 | 屋久島世界遺産地域等における森林生態系に関するモニタリング調査等に係る業務を実施 |
| 2016年 | 熊本県の認定鳥獣捕獲等事業者(熊本県第002号)を受ける 2016年から山都町での国指定天然記念物「ゴイシツバメシジミ」の調査に取り組む 2016年から林野庁の森林吸収源インベントリ情報整備事業 土壌等調査(資料収集分析業務)(九州ブロック)を実施 |
| 2017年 | 2017年から福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業(英彦山)事業に取り組む |
| 2018年 | 2018年~2019年の間で熊本県九州山地カモシカ特別調査を実施 |
| 2019年 | 熊本県シカ生息状況調査業務委託を受注する |
| 2020年 | コウモリ捕獲用ハープトラップを自社開発、併せてコウモリ調査用機器を充実させる 併せて新規のコウモリ調査用機器を導入する |
| 2021年 | 出水市ツル保護対策事業に取り組む |
| 2022年 | 照葉樹林復元のためのシカ被害対策に係る行動・生息状況把握調査業務に取り組む 熊本県SDGs登録事業者の認定を受ける |